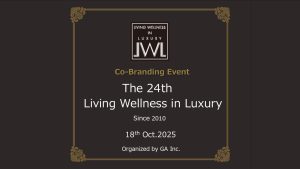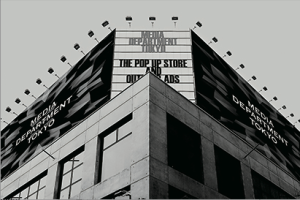多様性、インクルーシブを“自分ごと”として想像する展示会~東京写真美術館「遠い窓へ 日本の新進作家 vol.22」~
fy7d(エフワイセブンディー)代表/遠藤義人

多様性が叫ばれる一方で、実際にはSNSなどには異なる価値観への攻撃的な表現が目立つ。ほんらい民主主義の根底にあるべき基本的人権の尊重(個人主義)の精神は、アートの世界では他者への寛容を意味する。そんなことを想起させてくれる展覧会「遠い窓へ 日本の新進作家 vol.22」が、東京・恵比寿にある東京都写真美術館で2026年1月7日まで開催中だ。
東京都写真美術館は、写真・映像の可能性に挑戦する将来性ある作家を支援しその活動を紹介する「日本の新進作家」展を2002年より継続的に開催しており、今回で第22回を数える。今回選ばれた5名の作家の作品は、多様性を尊重するインクルーシブな理念とは何かを観る者に突きつけるものばかりだ。

東京都写真美術館の学芸員・大崎千野さんは次のように語る。
「写真や映像というメディアを通じて、私たちの身近な生活の中で生まれる小さな物語が、一人一人が大切にしている物事への想像を巡らせるきっかけになればというところから企画がスタートしました。多様性やインクルーシブな社会が求められているいま、異なる価値観を持つ人々とのコミュニケーションや共に生きることへの想像力が一層重要になってきていると感じています。異なる背景を持つ他者とすれ違い、無数の物語が交錯する中で、その物語に心を向ける機会はなかなか得られないのではないでしょうか。本展はそうした見えないもの、無数の物語や遠くにある誰かの暮らしや、大切にしている物語に心を向けようとするものです。今回の作品が窓となり、遠く離れた時間や場所、風景、記憶へと導くべく、風習や土地、記憶、家族、時代の流れといったものと結びつきから生まれた物語に焦点を当てて制作された5名の新進作家による写真や映像作品をご紹介いたします」
寺田健人 無意識にすり込まれている「当たり前」「らしさ」を問う
この作品は、寺田さんが「妻と娘にケーキを買って帰る」等、“想像上の”家族と暮らした日々の記録だ。透明な妻と娘、自身が父親という設定で、家族写真とオブジェクトをステージごとに制作している。
寺田さんは幼少期に自身を女の子と思い、父親にはなれないし子どもを育てることもないまま今を生きていることへの自問自答という感覚で、この作品を生み出したようだ。
「本格的に制作を始めたのはコロナの時期です。ステイホーム=家族と過ごせと言われた時に、LGBTQ+などのパートナーとして認められていない人はどうしても置いてけぼりになる。多様性やさまざまな家族の形があると言われていますが、実際はどうなのかを問い直したいと考えたのです。妻と娘にあたる部分が透明なことで、見る方のとっての、妻と娘やひとりでいる父親の捉え方を大切にしていただきたいと思っています」
日曜日の夕方に放送される「ちびまる子ちゃん」が描くステレオタイプな家族への“あこがれ”がタイトルに結びついているという。想像することは、失われたものを取り戻す行為であると同時に、自分にとっての“存在していいかたち”を確かめることでもある、という寺田さんの言葉にハッとする。


スクリプナリウ落合安奈 空気感まで伝える「ひかりのうつわ」
日本とルーマニア2つの母国を持つ落合さんが、パンデミック収束ととももに隣国ウクライナが戦禍に包まれた2022年12月から1年間、ルーマニアを旅した記録だ。
「冬にはじまりもう一度新しい冬が来るまでの1年間、様々な出会いがありました。ルーマニアはとても素朴な国であり、日本に住んでいるとなかなか見えない鮮やかな生と死を、単なる情報ではなく感覚として体感できました。国や文化といったものを超えた、現地の人びととの関係、土地の空気感を、この写真やインスタレーションを通じてイメージしていただき、皆さんが今まで生きてきた人生やこれからの人生に少しずつ重ね、思い出していただけたら嬉しいです」
暗闇にカシャッカシャッとスライドが無限に切り替わるさまは、現地でシャッターを切り時を刻んでいる感覚を味わえ、輪廻転生さながら。

甫木元空 ハーフサイズカメラが紡ぐ“映画的”表現
甫木元さんは、余命宣告を受けた母親が暮らす高知に移住し2017年から2021年にかけてハーフサイズカメラで撮影した作品を展示した。
それまで母親にカメラを向けたことなどなかったという甫木元さんは、民俗学者の宮本常一さんがハーフサイズカメラを愛用し記録していたことを思い出し、実践したと言う。
「この2枚1組というだけで、ある種すごい映画的だと思いました。母親が亡くなっても、写っている景色はいまもそこにありますし、カメラというある種の窓を通すと窓の外の風景は時とともに変わり続けていく。同じ場所でまたシャッターを切っても、いつも通りだが違う風景が外にはある。波を寄せては返すように、誰かの死というのは自然の一部であると同時にパーソナルな話ですが、それをまた見た方がどう思われるのかを楽しみにしております」
甫木元さんは映像と写真の違いについても触れ、映像では制作者が意図したタイミングで見せることができるが、写真はどの順序でどのタイミングで見るかが自由なところが残酷だと述べていたのが印象的だった。

岡ともみ 消えゆく風習“葬送”に目を向けた「サカサゴト」
12の柱時計の振り子部分に映像が再生され、時計の針は逆回転している…。
岡さんは、自ら祖父の棺に手向けたあじさいが火葬を経た遺骨を薄青に染めたことから、日本各地に存在した風習「葬送」を調査することを思い立ち、この作品に結びつけたという。
「“逆さごと”は、着物の右前と左前を逆さにするというような、古来から日本に多く見られる風習で、死者の世界 =異界と現世を分けつつ、慮るために存在しています。それらは、未だに残っているものもありますが、多くは現存しなかったり形骸化しています。昨今の葬儀がいい意味でも悪い意味でもスムーズかつ画一的に進んでしまう中で、日本の古来に少し立ち返ってみると、地域や人、集落ごとにさまざまな送り方や価値観が存在していたんです。それをお伝えすることで、人の送り方や儀式のあり方を考えるきっかけになればと思って制作しました」
とかく遺された者に迷惑を掛けない終活ばかりが叫ばれるが、誰にも必ず訪れる大切な人の死。送る側の慈しみの視点こそ大切にしたい。


呉夏枝 太平洋の過去と現在、事象の裏と表をインスタレーションで表現
日本とオーストラリアを拠点に活動する呉さんは、写真を転写した布とプロジェクションを駆使したインスタレーションを行う。
染め物のように見える布にはサイアノタイプという技法を用いて2種類の写真が転写されている。ひとつはオーストラリアの機関が所有する1910〜40年代の写真アーカイブ、もうひとつは現在のオーストラリア・マングローブの風景だ。
またプロジェクション映像は1798年にイギリスで出版された地図で、いわば帝国主義の象徴である。
これらにより、太平洋を住処とする海鳥たちが見たであろう景色を想像することで、現在と過去、撮影者と被写体、鑑賞者の関係性を問う作品となっている。
「自分の撮影したマングローブの写真は、いま自分が住んでいる場所を表しています。その裏側に転写された過去のアーカイブ写真を通すことで、自分の訪れたことのない太平洋の島々の風景を想像できるのかが制作に至った背景です。アーカイブ写真を使用したのは、過去の様子を伝えるだけではなく、今どのように変化したのかを想像することになりますし、過去の出来事が今につながっているというということも表現したいと思ったからです」
いまある領土状況や気候変動といった世界情勢は、すべて過去の歴史と地続きである。そうしたものに思いを致し、事象のウラオモテを考えさせる作品である。


東京写真美術館開館30周年記念「遠い窓へ 日本の新進作家 vol.22」は、2026年1月7日まで開催中。
[開催概要]
- 会場:東京都写真美術館3階展示室
- 東京都目黒区三田1-13-3恵比寿ガーデンプレイス内
- TEL:03-3280-0099
- 会期:2025年9月30日〜2026年1月7日
- 開館時間:10時〜18時(木・金は20時まで、1月2日は18時まで)、月曜、年末年始(12月29日〜1月1日)休館
- 主催:東京都写真美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、東京新聞
- 協賛:東京都写真美術館支援会員
-
fy7d(エフワイセブンディー)代表
遠藤義人
ホームシアターのある暮らしをコンサルティングするfy7d(エフワイセブンディー)代表。ホームシアター専門誌「ホームシアター/Foyer(ホワイエ)」の編集長を経て独立、住宅・インテリアとの調和も考えたオーディオビジュアル記事の編集・執筆のほか、システムプランニングも行う。「LINN the learning journey to make better sound.」(編集、ステレオサウンド)、「聞いて聞いて!音と耳のはなし」(共著、福音館書店。読書感想文全国コンクール課題図書、福祉文化財推薦作品)など。